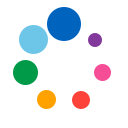関西はやっぱりおもしろい
そのクリエーティブパワーを探る(前編)
2014/12/18

多様な歴史と文化を誇り、独自のエネルギーを生み出してきた関西。広告・コミュニケーション分野も例外ではない。道頓堀のネオン看板は観光名所となり国内外で有名だ。また、“おもしろい”CMを多数輩出し、そのパワーは世界の広告賞も認めている。関西が生み出す広告の力の源泉は何なのか。クリエーターの声とともに、最近のトピックスを紹介する。




つい人に話してみたくなる、一点突破のアイデアが印象的な古川雅之氏。片や、さまざまなメディアを組み合わせた立体的な企画で、多くの話題を生み出している中尾孝年氏。電通関西支社内では、「Dentsu Kansai S-Creative」(エスクリ)と称し、特別編成の「チーム古川」「チーム中尾」をそれぞれ率いています。二人が考える、関西クリエーティブの「おもしろさ」、制作に込めた思いを聞きました。
関西クリエーティブ、原点へ立ち返る
──OCC(大阪コピーライターズ・クラブ)は今年、副会長になられた中尾さんをはじめ幹部陣が一新され、「『オモロイ』と『おもしろい』はちがう。」と宣言をしました。これにはどんな意図があるのでしょうか?
中尾:今までの伝統的な関西らしさを否定しているわけではないんです。ただいつの間にか、特に若いクリエーターたちが、単なる枠組みとしての「オモロイ」ことを目指すようになってしまった。そうじゃなくて、もっと自由奔放にやっていい。そもそも関西らしいオモロさは、個性ある先輩方が自分らの「ええな」と思うことを常識にとらわれずに追求した結果、出来上がったものなんで。こんなん無理やと言わんで一回聞いてみたろ、といったチャレンジスピリットに基づいているんです。だから、その原点を見失わないように、規定し直したという感じですね。オモロイことも含めて、人のいろいろな感情を揺さぶる広告を「おもしろい」と定義して、評価しようと打ち出しました。
──古川さんは、今年のOCC賞の審査委員長を務めてみて、いかがでしたか?
古川:何を「おもしろい」と思うかは、人によって全然違うわけで、今回の審査ではその視点をそれぞれ突き詰めている人が集まりました。自身が広告を作ったりそれをジャッジするときに何を基準にしているかをさらけ出し合っての議論になり、暑苦しくも意義のある審査会になりました。関西で必死にものをつくっている現役の面々が「おもしろい」と感じるものを選ぶ、というのが結果的に審査基準になったというか。
中尾:僕が新人のころ、特にクリエーティブは関西希望の人が多かったんですよ。ちょっと異質で、しゃくし定規にやってたまるか、っていう人たちが集まっていて。でもここ数年、関西の広告づくりがだんだんシステマチックな雰囲気になっていって、やっぱり東京に行かんと日本を動かせへん、みたいな傾向が若い世代には出てきている。それがすごく気になっています。
──そんなことはないのでは。
中尾:ないですよ。日本どころか、実際にOCCに集まる広告でも、電通関西支社が関わった広告でも、割合でいうとめちゃくちゃよう当たるくじくらいの率で世界の賞を取っています。直近でも、古川さんがつくった赤城乳業「BLACK」のめっちゃゆるいCMが「アドフェスト」と「スパイクスアジア」のフィルム部門でブロンズを受賞しました。むしろ今はウェブが広がって、ほんまにおもしろいものなら場所を問わずに世界から注目が集まるし、人も動く。そこにもっと気付いてほしいと思いますね。
ヒントは自分の身の回りにある
──OCCの宣言の一つには、「世界を意識します。」という項目もありますね。
古川:僕はまったく意識していませんでしたけど(笑)。
中尾:意識していないのは分かるんです。自分がおもしろいものを追求してはるなと思う。大事なのはそこなんですよね。どこにいても世界につながるようになりましたが、「世界を目指そう」とか、賞を取るための傾向と対策っていう方法論には、僕は違和感があります。それは何だか広告の本質とずれてるな、と。せやなくて、純粋にええ広告をつくろうと、日本のみんなにおもしろがってもらおうと思ったら結果的に世界中が笑いよったという、そういうつくり方をしたいなと思うんです。
古川:確かに、何か賞やほめられることを目指したり、誰かまねごとをしてつくっても、なかなか全力は出ないという気はします。今までそこで随分悩んだし、道に迷いました。自分らしさ、というのがいちばんムツカシクって。世界のことで言うと(笑)…「ローカルやマイナーを突き詰めればグローバルになる」と教えてくれた大先輩がいます。人間のおかしみみたいなところを自分ならではのすごく狭い視点でギューッと煮詰めて描いたら世界にも伝わる…ということがあるかもしれません。
──古川さんの広告は、1回見たら忘れられないクリエーティブが特徴的ですが、今言われたように、いつも自分の視点を突き詰めて考えているのでしょうか?
古川:そうですね…、そうありたいと思いつつ、七転八倒して結局もう最後それしかできなくてたどり着く、という感じですが(笑)。僕がいつも思っているのは「広告は誰も見ようとしていない」という、先輩から刷り込まれた原則です。だから、振り返ってもらうために、ほとんどの力を使わなあかんと。それと、広告は費用対効果だと教わってきました。100回より3回、もっと言えば1回見て人に言いたくなる方が得。そう考えると、「インパクト」とか「目立つ」っていうことになるんですが、自分なりの「インパクト」をみんな探し続けているんだと思うんです。でも、言葉にしたとたんに、壮大過ぎて「インパクトインパクト…インパクトって何だ?」と思考停止するときもあって。
中尾:企画書に「とてもインパクトがある○○です」って書いてあるのは大抵おもろない(笑)。
古川:そうそう、不安だから言葉にして自分で言ってしまう(笑)。だから、インパクトと言葉で書く前に、具体案を出すしかない。これも先輩からの受け売りですが、自分にとって珍しいものとか、自分の周りの人に見せたときに笑ってくれそうだとか、自分の身の回りのことで考えていくんです。そのとき、やっぱり自分の好きなものや関心があるものにヒントがあるような気がします。僕だったら個人的にはナンセンスとかシュール、ギャグとかが好きなんですけど、広告とはなかなかそぐわないそれらと、広告する商品、世の中との接点を探していきます。それはもう泥沼です(笑)。もがけばもがくほど深みにはまったり…。
自分ならではのアイデアで楽しんでもらうには
中尾:若手やOB訪問に来た学生に、よく発想法とかノウハウを聞かれるんですけど、10個の案件があれば全部違うのが僕らの業界ですよね。
──発想法を聞かれて、どう答えられているんですか?
中尾:おもしろいアイデアを思いつく唯一の方法は、おもしろいことを思いつくまで考え続けるしかないんじゃ!と(笑)。最近は、考えろというと、みんなすぐ検索し始めますが、検索だと自分の発想は広がらないので、あんまり良うないですね。一つ言えるのは、自分が楽しいと思える企画になっているかどうかだけは、基準にしています。いちばん攻略しやすいターゲットって自分やと思うので。後は、どうやって楽しんでもらおうかな、とすごく考えています。
──中尾さんの仕事には、江崎グリコ「アイスの実 江口愛実キャンペーン」など立体的な企画が多いですが、そういう仕組みで楽しませるということですか?
中尾:いえ、仕組みありきではありません。僕はマスとウェブを組み合わせた仕組みでコミュニケーションする人やと言われていますが、強いアイデアが一つあれば仕組みは要らないと思うんですよ。でも、僕が古川さんみたいに一発ですごくおもしろがられるアイデアを出そうと思っても、絶対にかなわない。自分ならではのアイデアで、十分楽しんでもらうためにどうするか、と肉付けした結果がああいった形になっているんです。
古川:僕は…最終形が割とヘンてこなものやゆるいものが多いので、適当に考えてるか全く何も考えてないかどっちかだ、と思われそうなんですけど(笑)、考え始めるときはいつも、実際の売り場に行ったり商品を使ってみたりして、何を言ったら振り向いてもらえるか、買ってもらえるかを毎回真剣に悩んでいます。正攻法で。後は、思いついたことをとりあえずやってみる。最後の最後まで不安なんです。おもしろいと思ったものが、実際やってみるとおもしろくなかったらどうしようとか。昨日まですごくおもしろいと思ってたけど、実はまぁまぁじゃないかとか。だから試しにネットで似た動画を探して音声を当ててみたり、テスト撮影とかもよくします。それでも現場で「あれっ?」ということはあるんですよね。イヤな汗が出る。もう、いっぱい準備しておくしかない。
中尾:現場でおもろなかったら、捨てる勇気って要りますよね。だから、そこで「これちょっと変えましょうか」って言える、クライアントさんとの信頼関係が重要なんです。
古川:それも、僕らの大事な仕事ですよね。まぁそう言うなら一回やってみれば?と言ってもらえる関係に随分助けていただいています。関西では僕ら含めてクリエーターが営業と一緒に直接クライアントさんと話すことが多いので、その場でディスカッションして案が生まれることもあります。求められているものに対しては、どんな形でも何らか応えて、喜んでほしい。サービス精神が過剰なんですかね(笑)。
──これからは特にデジタル領域の発展によって、企業のコミュニケーション環境も変わっていきます。そうした変化も含めて今後の展望を教えていただけますか?
中尾:企画の視点では、デジタルはあくまで手段の一つなので、そのときどきに応じてより楽しんでもらうために有効に使っていきたいと思いますね。環境という部分では、場所を問わずいろいろなことを仕掛けられる選択肢が増えたのでありがたいですし、どの地域のクライアントにとってもチャンスになります。その一方で、だからこそ一つ一つのコンテンツのおもしろさが問われているので、なおさら仕組みに甘えずに、個々で魅力的なものにせなあかんと思います。
古川:僕も、解決策にデジタルを使うというケースは増えていくとは思いますが、デジタルだけだとやっぱり狭いと思います。例えば自分の両親のようにデジタルに精通していない高齢者は、自ら積極的に話題の動画を見ることもないだろうし、デジタルにまだ接していない小さな子どもには届かない。テレビの得意なところ、デジタルの得意なところを見極めてうまく使いわけていく、もしくは組み合わせていくということになってきていると思います。テレビVSウェブと言っていたのはもう一昔前の話で、SNSを含めておもしろいコンテンツが作れれば一気に拡散する準備が整った今、テレビとウェブの融合でどういうことが可能になるか、自分なりに探っていきたいですね。

古川氏が手掛けた梅の花「夜は夜の梅の花」編。計算されたシュールな世界観の作品で2010年ACCグランプリを獲得した。その後、歌モノののシリーズを多数制作している。

古川氏が手掛けた赤城乳業・BLACK「じゃない」編。個性的なキャラクターやナンセンスな歌、不思議な踊りでロングセラー商品をアピール。売り上げは250%になった。

中尾氏が手掛けた江崎グリコ「アイスの実」キャンペーン。AKB48のメンバーの顔を組み合わせた謎の新メンバー「江口愛実」が実在するか否かで話題に。国内外で高い評価を得た。

中尾氏が手掛けた塩野義製薬「もしもブラマヨの吉田がもっと早く皮フ科へ行っていたら…」編。CMと同じ設定で架空の漫才コンビやトレンディー俳優の記者会見も企画し、多メディアで取り上げられた。